10月
2013年10月10日
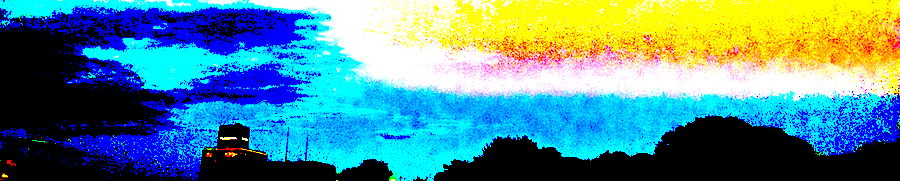
台風来ないかなと、予報を見ている限りきっと来るのだろうとわかりながら私は教室の窓から半身を乗り出して空を仰ぐ工藤夕貴の姿が思い出されて、その翌朝に同じ教室の同じ窓から飛び降りることになる三上祐一がその死の直前に厳粛な生を生きるための厳粛な死が僕たちには与えられていないというその現状を嘆きとも異なる調子で唱える姿もまた同時に思い出され、その二つの時間のあいだに夜の校庭の乱痴気騒ぎがあることも思い出されたが、その場面はどこか透過化されたような、薄い皮膜の次の層に置かれたように見えたのもまた事実だったし、その夜、期待したような強い風や横殴りの雨というのはまだ見られない夜、傘を二つ手に持った私はそれらをライフル銃に見立てて手当たり次第に、ちゃんとどこかを狙っているようにはとても見えない格好で撃ち続け、次第にその歩みの速度を上げ、駆け出し、なおも撃ち狂い、最後に(深夜に合わせて落としたトーンで)絶叫するという真似をして自転車をゆっくりと漕ぐ彼女に「はい誰の真似でしょう」と言うことになるが、それはその日の朝のバス停のベンチに黒いサングラスをかけた白髪の、レオス・カラックスに似た年齢不詳の男を見かけたからに他ならなかった。屋根のある、こぎれいなバス停にその男は座っていて、ちょうどよくやってきたバスに乗らなかったところを見るともしかしたら夜が来るのを待っているのかもしれなかった。私たちはそうやって物真似をして家路につき、二人でソファに並んでOMSBのアルバムを聞きながら「かっこいいね」と言い合うのかもしれなかったしそれは何日か前の昼間の出来事だったのかもしれなかった。そんな時間が現実にあったためしはないのかもしれなかった。けっきょく書かれることが何であろうとも私は構わないのだった。書くことは私にとってはセラピーのようなもので、こうやって打鍵を続けること、それ自体が必要とされているらしかった少なくとも今の私のモードにとってはそれはそのとおりだったし「貧しさ」を事件として生きながら、収奪の二重構造が具体的に機能しつつある限界的な一点に不意撃ちをくわえ、わずかなりとも可視的な領域に露呈せしめんとする試みをここで改めて「批評」と呼ぶならなどという、打ち震えるほどに格好のいい文章を書くことができないとしても何一つ悲観することはなくて、ここで引かれた蓮實重彦の『表層批評宣言』を夜ごとちまちまと読みながら重力の重みによってまぶたは次第に閉じられ、気を失ったあとに見る夢は決して恩寵ではなく悪夢の類である場合が多い今となってみても、そのことに一つの意味合いを持たせるように昼の人生を暮らすわけでもなく、悲観ではなく静観を、メロドラマなどでもなく、窓の、外に映るいくつかの光、反射する店内、そこに見えないものを見ようとする惰性を排し、ペラペラのその表層を見つめ続けようとして努力してみせること、舞城王太郎のおそらく『みんな元気。』で書かれていた恐怖を克服するためには恐怖の根幹を見つめること、その教えを、私はわりと今もまともに愚直に信じている。見つめること。シンプルに。それは染みであり、それは反射であると見つめ知ること。同時に読み始めたロベルト・ボラーニョの『売女の人殺し』の中でも同じようなことが書かれていて、Bは一瞬、白いワンピースの女を見つめながら(このとき初めて女がとても美しく見える)、ナチスの賛歌が血の色をした空へ昇っていくあいだ、まるで従順な子羊のように地上から跡形もなく姿を消したギー・ロゼのことを考え、そして自分自身がギー・ロゼに、アカプルコのどこかの荒野に埋められ、永遠に消え失せてしまったギー・ロゼのように思えるが、そのとき、父が元ダイバーを何か咎めている声が聞こえ、自分がギー・ロゼとは違って孤独ではないことに気づく、とある「この世で最後の夕暮れ」は父と子の短い休暇の様子が淡々と綴られた作品だが、ボートが転覆しても死ぬことにはならず、賭けポーカーで勝ち抜けしようとしても死ぬことにはならないそのバカンスのあり方を、プールサイドで出会った初老の婦人と寝る逞しい父の姿を、私は今一度信じてみたいとそのようにたった今思った。これはいずれもとても好ましい出来事だったしプールサイドで何かの実験とfla$hbacksのjjjが言って、それをつい先ほどまでこの耳は聞いていた。彼らのアルバムは何を歌っているのか何度も聞いているけれどさっぱりわかっていないのだけれども私の耳にはひたすらに都合よく響き続けるため何度でも聞いていて、febbのソロアルバムはいったいいつになったら出るのだろうかと心待ちにしていた矢先、ホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』が出版されたことをhontoカードのメールがお知らせをしてくれて、『売女の人殺し』と同じ松本健二訳ということでよく仕事をされていることがわかるし、次に読むものはこれか、あるいは『売女の人殺し』を買いに日曜の晩に行った本屋で、どうにも見つからず、クソみたいな本屋だと嘆きながら店員の方の姿が見当たらなかったため店内に響き渡る大声で「売女の人殺しは置いてませんか、売女の人殺しは置いてませんか」と言ったのだが誰も取り合ってくれなかったため仕方がない格好で保坂和志の『未明の闘争』を買ったのでそちらを読むかもしれないけれども、今年いっぱいは少なくともずっとラテンアメリカのものを読んでいたいような気がするというか、今現在蓮實重彦も読んでいるのであれなのだけど、小説に関してはラテンアメリカのものだけを読みたいような気もしているから『未明の闘争』はいつ読むかわからわないしいつか読み始めたらいつだって泣く準備はできているようなメンタリティの私は何かを決壊させたりするのだろうかとか、今まで保坂和志で泣くという経験はしたことがないにもかかわらず妙な期待をしている部分があり、書き出しの一文で「何やらものすごい」みたいなものを与えてくるらしい小説としてピンチョンの『重力の虹』がよく引き合いに出されるというかよくかどうかは知らないけれども何度かそういう場面には出くわした記憶があるけれど、ボラーニョのそれだって引けをとらないというか、まだ3編しか読んでいないけれども、奇妙なことに、マウリシオ・シルバ、通称目玉は、たとえ臆病者と見なされる危険を冒してでもつねに暴力から逃れようとしたが、暴力、真の暴力からは逃れられないものなのだ、というのが最初の「目玉のシルバ」で、人生最悪のある時期、僕はゴメス・パラシオを訪れた、というのがその次の「ゴメス・パラシオ」で、「この世で最後の夕暮れ」は状況は次のとおり。BとBの父は、休暇でアカプルコに出かける。早朝、午前六時に発つ、という感じで始まるが、何がぐっと来るといえば、それぞれ、マウリシオ・シルバ、ゴメス・パラシオ、アカプルコであり、つまり見慣れない地名であったり人名であったりのカタカナたちであり、それだけで私の中のフィクションのエンジンが駆動されるような、小説の中にぐっと引き寄せられるような、時間と場所から解き放たれるような、そういう心地がある。それはとても好ましいものだ。翌朝、空は晴れ渡っており、楽しみにしていた台風はどうも終わったか、逸れたかしたらしかった。店に向かっているといつも顔を合わせ、おはようございますと言い合う仲の人がやはりその朝にもいたので台風はどうなったのですかと尋ねてみるともう隠岐の島の方に行って、思ったよりも速く動いていったみたいで、というようなことを教えてくれたその日、私たちはいつものように働き、昼寝をし、夜まで楽しく働いた。どれも、極めて好ましい出来事だった。私の人生は好ましい出来事の連なりとして基本的に構築されていると頑なに信じる姿勢を崩したくはない。以上すべてを同時に考えながら家に帰った私は一目散に服を脱ぐと、「やれやれ」とつぶやき、シャワールームに入った。両手を壁につけてうなだれた後頭部に42度のシャワーを浴びながら、村上春樹はジャズ喫茶をやっていたらしいけれど、一日の売上はどのぐらいのものだったのだろう、と考えた。営業後に小説を書いていたというけれど、体はしんどくなかったのだろうか、とも考えていた。