11月
2013年11月5日
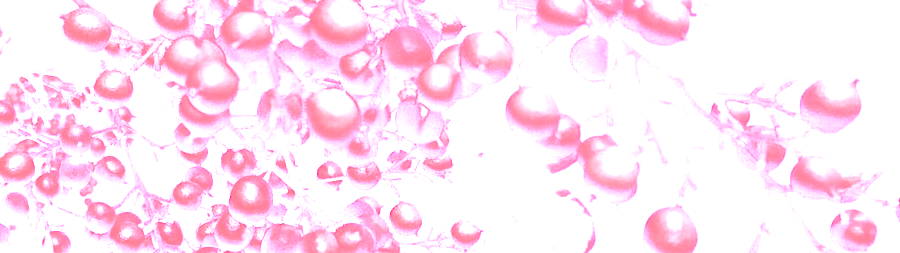
古本をあまり買わないのは私の読書行為はカバーのついた本を読み、読み終えたらカバーを外す、本棚に収める、までが入っているというところが大きくて、だから基本的にはカバーのついていないAmazonで買うことはなくて、どこかの本屋で買ってカバーをつけてもらうという流れがあるのだけど、それ以外にも古本屋を利用しない理由としては買ったところで著者なり出版社なりにお金が回らない、それはきっといいことではないだろうという認識があるためというのがあって、一冊売れたところでの影響などたかが知れているのはそれはそうだろうけれども、私は少しでもそれを作った人たちに何かしらの還元をおこなえるのならばおこないたいのでそうしている。だから古本屋で買う本というのはノーマークで、偶然見つけて、そこで偶然見かけなかった限りは買わなかっただろうという場合にだいたい限られていて、そこで買うのは、サンキュー、古本屋さん、出会わせてくれて、というところがある。
そういう気分は持ちながらも、珍しく、一週間のあいだで二度も古本を買うということをおこなった。一つ目は最近出来た古本屋で、そこはサブカルなものが好きなんだろうなあという色合いのお店で、色があるというのは好みの別はあれいいことだなと思いながら、あまり好みのものは置いていないと思いながら、なんとなく中原昌也の自伝と暴力温泉芸者のCDと高橋源一郎の小説を買った。二度目は昨日の朝に家の近所の公園でマーケット的なものが催されていて、それは愉快な催しだなと思ったし、人見知りながらもちゃんと知った人に出くわせば「あ、おはようございます」ぐらいは言って、以前同じ催しに行ったときに知った人に出くわして挨拶をし続ける状況に辟易というかしんどいと思っていたのが嘘のように、朝の爽やかさに乗せられる格好でそれなりに爽やかな気分を維持しながら挨拶することができたのだった。そこで古本屋も出ていて、一つは面白いと思えるものが置いていなく、並ぶ本を見ていてもけっこう残念な気分になるというか、なんというか、何が並んでいたのだったか忘れたけれど、ある種のブックオフ的な品揃えに見えたというか、少し前に話題になったような本の、古本とか古書とかいうよりは中古品といった方がニュアンスがわかりやすいような気がするのだけど、それは例えば村上春樹の岬がどうのこうのみたいなタイトルだったと思ったけど今検索したら岬なんていう文字はどこにも入っていなかったのだけど、それが印象的というか決定的というか、村上春樹を置くのがダメというわけでは全然ないのだけど、というか、だからここで村上春樹の名を挙げるのはフェアじゃないような気もするのだけど、なんだかとても、あーはいはい、という気持ちになったというか、あの本はたぶんあの日、誰かが買うのだろう、絶対誰かが買うはずだ、それは「中古」で、いくぶん安く手に入るからだ、という、確信めいたものが、あーはいはいを助長させたというか、ともかく、古本屋は、何を置くかということも当然大事だろうけれども、何は置かないかということもすごく大事というか、あーそれ置いちゃう、というのを感じてしまうと一気にだるい心地になるというか、それはもちろん、商売でやっているのだから売れる本を置くのは大事だとは思うのだけど、いや、古本屋であればその商売上、何を売りたいのか、何を売る店だと認知されたいのか、みたいなのがある方が商売上もやっぱりいいのではないかと思うのだけど、なぜならばあの日あの場所で村上春樹の中古本を買った人は、その店がなんという名前で、どこに行けば買えるかを知ろうとすることは絶対にないと思うからで、一方でもう一つ出ていた古本屋では、私たちはそこで何冊か買ったのだけど、コンラッドの『密偵』だったかな、そんな感じのやつとボルヘスの『夢の本』だったかそんなタイトルのやつと、あとなんだったか、とにかく何冊か買ったのだけど、私はそこで本を買ってから、のちに検索してどういう古本屋なのか、そこでは他に何を買えるのかを調べることになった。それは商売上、客の動きとしては悪くない動きではないだろうか。ということだった。
それにしても、古本屋とか先日あったというか毎月やっているらしい古本市とか、覗くといつも思うのだけど古本屋の人たちは幻想小説というのか耽美小説というかそのあたり全然わからないのだけどそういった類の小説がすごく好きだよね、という印象を受ける。サドとか澁澤龍彦とかバタイユとか、わからないけれどもなんかそういう感じ大好きだよねといつも思う。べつだん強く興味をそそられないけれど別に嫌だとかは思わないのだけど、外国文学っていったら幻想とか耽美とかそういうものでしょみたいな空気があったりするのだろうか。中原昌也とかを買った古本屋でも、外国の小説はほとんどなかったにも関わらず『ソドムの百二十日』以下そのたぐいのものはあって、ちょっとモヤモヤするところがあった。べつだん強く興味をそそられないけれど別に嫌だとかは思わないのだけど、どうも、なんだか、ファッションとしてのそういう類の小説という部分があるようにどうしても感じてしまって、そう感じてしまうと一気に気持ちが悪い。
なんでもそうだけどファッションとしてやってるでしょーそれ、みたいなものが透けて見えてくると気持ちが悪いもので、結局、ファッションとして、外皮に装飾を施す行為として何かをやっているように見えるものに感じるのは、そのコンテンツそのものを本当に信じてはいないのではないかという疑念であり、それは古本屋の品揃えに限らず、何かしらに対する発言だってそうだし、催されるイベントにしたってそうだし、なんだってそうだ。本当に信じないと、のめり込まないと、大好きだと、絶対にこれは良いものだと、確固たる姿勢で言えなければいけないなどとはまるで思わないのだけど、信じてなどいないものを不器用に装飾して提示されても薄ら寒さしか覚えない。信じていなければいけないなどとはまるで思わないというのは、信じていなくても全然いいからせめて信じきっているような華麗な嘘をついてほしいということで、ほしいというか、うまく嘘をついたらいいのにな、というところで、往々にして、信じていない人は全然うまく信じているふりをすることができない。ここのところ、そういう、目の前のコンテンツの力を根本的に全然信じられてないんだろうなー、ただの利用する対象ぐらいの感じなんだろうなー、みたいな気分になることがあり、なんだかなー、それ、いったい誰が幸せになるの、と思うのだった。
ファッションなんて犬にでも食わせとけ、というところだった。